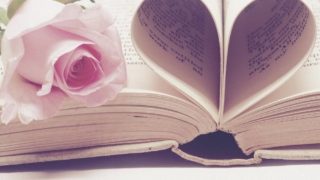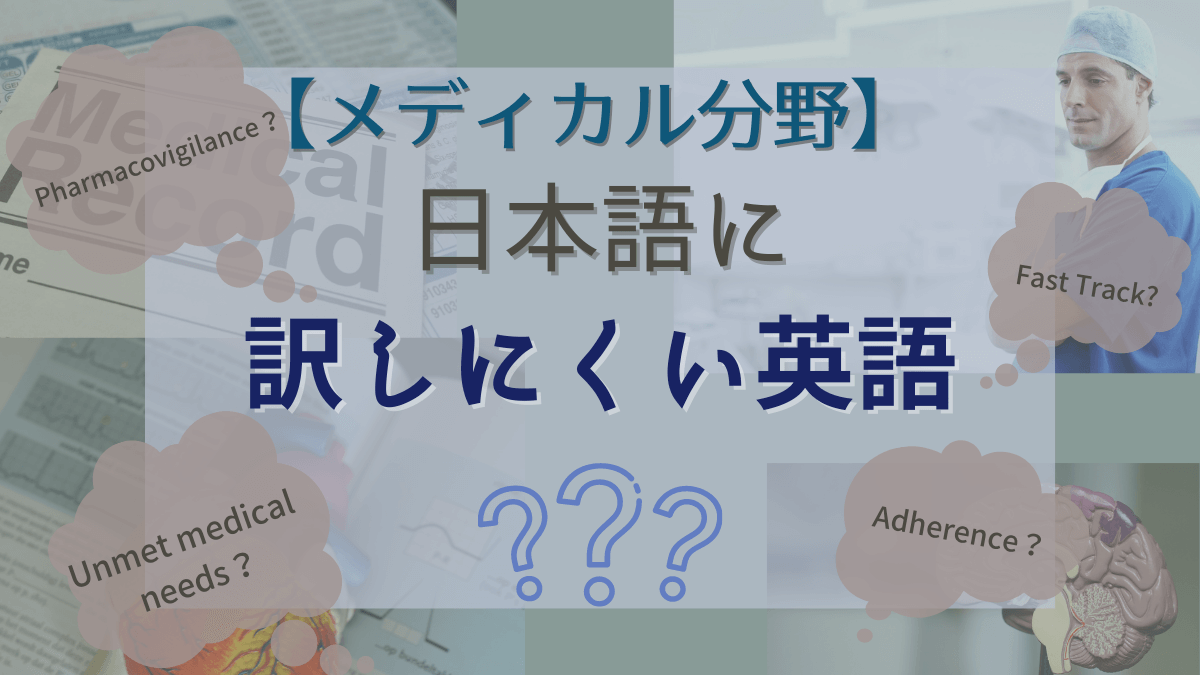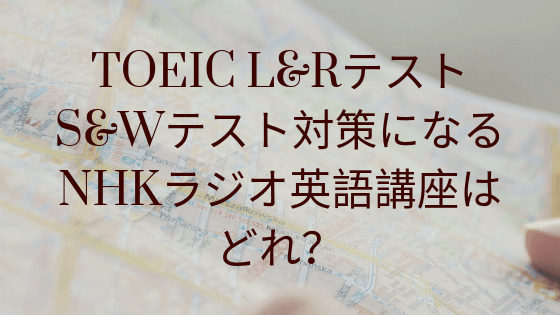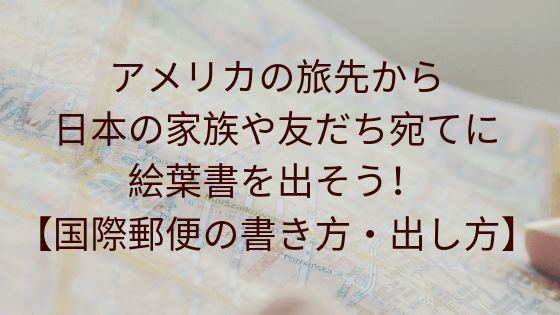グローバル化が進む中、海外と情報を共有したり、違う国籍同士で同じ課題に取り組んだりという場面も増えています。
しかし英語などの語句を日本語に訳そうとするとスパッと短く置き換えられないことも。
結局、カタカナ語となって日本語に定着する言葉もあります。
例えば「インフォームドコンセント」。
「インフォームドコンセント」とはご存じのように、「治療方針や病状などについて、医療専門家が患者・家族に説明を受けた上で、患者・家族が納得し同意すること」を言います。
日本医師会では『説明と同意』という用語を提唱しているとか。
しかし現在、広く使われているのは、「説明と同意」より「インフォームドコンセント」の方だと私は感じます。
この記事では、そうした「日本語に訳しにくい英語」のうち、医薬・メディカル業界で使われている言葉を解説します。
後半では、日本語に訳しにくい言葉を見事に訳した先人のお話と、私がメディカル翻訳を勉強した翻訳専門スクールからの耳寄りな情報をお届けします。お見逃しなく!!
日本語になりにくいメディカル英語
医療・製薬分野で使われる英語の専門用語は、ときに日本語にうまく訳せない語句があります。
一語で言い換えることができないために、単語をそのままカタカナで表記し、それが定着しつつある言葉もありますね。その一部をご紹介しましょう。
アンメットメディカルニーズ=Unmet medical needs
いまだ満たされていない医療上の需要
「meet」は「条件を満たす」とか「要求に合う」という意味ですが、その「meet」の受動態「met」が「un-」で否定されています。つまり「要望を満たしていない」ということ。
まだ治療法が確立されていない疾患や健康上の問題に対して「治療法や医薬品を開発してほしい」と患者さんや医療現場が考えていて、十分な治療満足度が得られていない状態、またはその治療や薬剤に対する強い要望を指します。
「アンメット」「アンメットニーズ」などと略されて使われる場合も。
アドヒアランス=Adherence
患者さんが治療方針について納得し、積極的に自分の意志で治療を受けること
コンプライアンス=Complianceという言葉もありますが、そちらは「患者さんが、医療専門家の指示通りに治療を受ける」という意味となり、受け身の状態ですが、アドヒアランスは患者さんがもっと積極的に治療に関わる意味になります。
しかし実際には、患者さんが医師や薬剤師の指示通りに薬を飲まない場合などに
「(服薬)アドヒアランスが低い/不良である」
と表現するなど、厳密に区別されない場合もあるようです。
ファーマコヴィジランス=Pharmacovigilance
医薬品の安全性を監視すること
日本語では「医薬品安全性監視」と訳されることがありますが、「ファーマコヴィジランス/ファーマコビジランス」のままでも使われています。
世界保健機関(WHO)により「医薬品の有害な作用または医薬品に関連する諸問題の検出、評価、理解及び予防に関する科学と活動」と定義されている。
―日本薬学会より
医薬品を意味する「Pharmaco-」と監視・警戒を意味する「-vigilance」を合わせた単語です。
ちなみに日本語でも「医薬品安全性監視」と言われてもピンとこないように、アメリカ人の英会話の先生に「Pharmacovigilance」と言ってもキョトンとされることがあります。
ファストトラック=Fast Track
必要性の高い新薬の審査を優先的に行う制度
医療分野以外でも、「新技術の迅速な開発や導入を促進する制度」のことを言いますが、メディカル分野では以下を指します。
優先審査制度の別称で、必要性の高い新薬の審査を優先的に行う制度。
―製薬業界の転職支援 アンサーズHPより
通常、医薬品の研究、開発には9~17年の時間がかかると言われています。
その間にいくつもの段階を経て、やっと医薬品は市販されるようになりますが、必要性が高く緊急度が高い薬剤に対して、途中の審査を優先的に行う制度です。
最近では2020年5月に、米食品医薬品局(FDA)が新型コロナウイルス感染症のワクチンの開発をファストトラックに認定しました。
レギュラトリー・サイエンス=Regulatory Science
科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学
レギュラトリーサイエンスとは、
「科学技術の成果を人と社会に役立てることを目的に、根拠に基づく的確な予測、評価、判断を行い、科学技術の成果を人と社会との調和の上で最も望ましい姿に調整するための科学」
(第4次科学技術基本計画 平成23年8月19日閣議決定)とされています。
ー独立行政法人 医薬品医療機器総合機構HPより
まだちょっとわかりにくいですね。
レギュラトリーサイエンスとは我々の身の回りの物質や現象について、その成因や機構、量的と質的な実態、および有効性や有害性の影響をより的確に知るための方法を編み出し、その成果を用いてそれぞれの有効性と安全性を予測・評価し、行政を通じて国民の健康に資する科学です。
ー日本薬学会レギュラトリーサイエンス部会HPより
…。正直に言って、わかるようでよくわかりません…。
クオリティ・オブ・ライフ QOL=Quality of Life
「生きること」「生活」「日々の暮らし」の質や快適さ
「(患者さんの)生活の質」と訳されることが多いですが、この場合のLifeは、単に「生活」というだけではありません。
精神的・身体的苦痛から解放され、社会的にも経済的にも負担を強いられることなく、どれだけ人間として毎日の生活に楽しみを見出せるか、自分らしくいられるか、充実感、満足感をもって日々を過ごせるかなど、生きる上でのすべてを包括的にとらえた『質』を意味します。
「クオリティ・オブ・ライフ」「QOL」という言葉は、すでにある程度、定着していますね。
「昔の日本人はすごかった…」吉村昭の小説を読んで思う
このように、日本語にしにくい英語というのはたくさんありますが、昔の日本人はこれらをなんとか日本語にしていたわけですね。尊敬。
吉村昭さんの小説を読むと、江戸時代の日本人の「英語を学ぼう」「英語を日本語に訳そう」という情熱、熱意、工夫に、本当に頭が下がります。
『冬の鷹』は解体新書を訳した前野良沢を主人公にした小説です。
例えば「神経」という日本語も、前野良沢が訳語として考え出したとか。
解体新書と聞くと杉田玄白の名前が上がりますが、吉村さんの本によるとむしろ前野良沢の功績が大きいようです。
※余談ですが、この中に出て来る平賀源内の最期は強烈です。私の中で平賀源内のイメージが変わりました。
『海の祭礼』は、日本に憧れ上陸したアメリカ人と、長崎で通詞(通訳)として開国に関わった森山栄之助らの物語です。
英語と日本語という全く違う言葉を話す人間同士が、生活を共にし、口伝えでお互いの言葉を理解していく…。
どちらの作品も、読んでいると
「こんなにテクノロジーが進歩した現代で『英語ができない!』なんて言ってたら、ただの甘えだな」
と思うくらい小説の登場人物の勤勉さ、熱心さに打たれます。
ぜひご一読ください。
「フェロー・アカデミー」なら全講座がオンラインで受けられる!
江戸時代と違い、現代に生きる私たちには、インターネットという武器があります。
そして2020年以降、COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響で、リモートワークやオンラインレッスンなども急速に普及してきました。
スキルを身につけたり磨いていったりするうえで、こうしたテクノロジーを使わない手はありません。
私が翻訳を学習している時にお世話になった「フェロー・アカデミー」でも現在、なんとすべての講座がオンラインで受講できます(2021年2月現在)。

自宅にいながらにして、現役エキスパート翻訳者の講義を受けられるなんて!
翻訳のスキルを身につければ、フリーランスとして在宅で働くこともできる!!
時代は変わっていくねー♪
私は48歳からメディカル翻訳を勉強し始め、受講開始から半年で、医薬品業界に就職しました。
翻訳講座は、就職前に4講座、就職後にさらに2講座を受講しましたが、そのうち2講座がフェロー・アカデミーの講座です。
詳しくは「未経験でも就職できた【医療メディカル翻訳おすすめ講座】在宅ワークを目指す人にも!」をご覧ください。
メディカル分野は、人が不死にならない限り需要があるジャンルです。
そして現在も、複数の国が参加する「国際共同治験」2が日々、増えているため、翻訳スキルを持つ人材は有利になっていきます。
この記事で紹介した「日本語に訳しにくい英語」もテクノロジーの進化に伴い、今後増えていくかもしれません。
(医療翻訳に携わっていけば、前野良沢が訳した「神経」のように、日本人が自然に使う言葉として訳すチャンスもあるかも!?)
メディカル翻訳は、他ジャンルに比べ報酬が高めで需要も多く、好きな英語を活かせます。
翻訳スキルを身につけて実績を積めば、フリーランスとしての働き方も開けます。
ただし残念ながら翻訳は、「英語ができる」だけでこなせる仕事ではありません。
わかりやすい日本語を書いたり素早く調べものをしたりといったテクニックなども重要になってきます。
そうした関連スキルや、講師・学校・翻訳仲間とのコネクションも築いていけるのが、スクールの講座を受講する利点の一つ。
まずは▼こちら▼から資料請求をしてみましょう!もちろん無料です!
「稼げるスキル」を最短で身につけるために、一歩を踏み出してください。